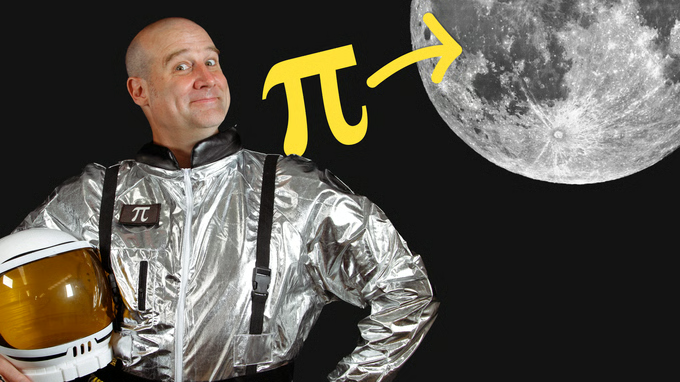クラウドファンディングサービス「きびだんご」を運営する松崎良太氏は、ユニークなプロダクトとビジネスを求めて世界中を旅している。
今回の出張で出会ったのは、フィンランドで腕時計ブランド「AndoAndoAndo」を立ち上げた日本人デザイナー安藤悠さん。「誰もが楽しめるインクルーシブな時計」を目指す安藤さんとの対話を通じて見えてきたのは、マイクロブランド(小規模独立系ブランド)という新しいものづくりの形と、クラウドファンディングとの高い親和性だった。(編集部)
AndoAndoAndoの安藤さんとヘルシンキで会ってきた
以前から仕事を通じてお話ししていた「AndoAndoAndo(アンドウアンドウアンドウ)」の安藤悠さんに、たまたま出張で訪れたヘルシンキのホテルで、初めて直接お会いし、お話を伺いました。
AndoAndoAndoは、日本人デザイナーの安藤悠さんがフィンランド・ヘルシンキで立ち上げた腕時計ブランドです。
安藤さんは大学で環境デザインを専攻するほど、ものづくりが好きでした。卒業後、一度はデザインの現場を離れましたが、日本とフィンランドでさまざまなプロジェクトに関わるなかで、優れた作品に触れるうちに創作意欲が再燃。
「メンズ腕時計は大きすぎて自分には着けられない。レディースは小さすぎて時間が見えない…」という自身の違和感から、「誰もが楽しめる腕時計を自分で作りたい!」という思いが芽生え、2019年にデザインを開始。試作を重ね、2020年にブランド「AndoAndoAndo」を正式に創設し、生産を開始しました。
性別も年齢も手首のサイズも関係ない「AndoAndoAndo」の時計づくり
安藤さんは「インクルーシブ」という言葉が好きだと言います。誰もが自分の居場所を持てるような、そんなものづくりを目指しているのだと。その姿勢は、プロダクトのサイズ感やデザインにもよく表れています。
長く厳しい冬が続くフィンランドでは、飽きのこないシンプルなデザインが日常に好まれます。その感覚はAndoAndoAndoのプロダクトにも反映されており、文字盤からあえてブランドロゴや細かな目盛りを排したミニマルな機能美が特徴です。また、ジェンダーレス先進国であるフィンランドらしく、誰もが使えるユニセックスなデザインにもこだわりが感じられます。
ブランド名「AndoAndoAndo」は、創業者の名字「安藤」を3回繰り返しただけのシンプルな名称。自分の名前を重ねることで、小さな家族経営ブランドならではの遊び心あるものづくりを体現しているようです。
ミッションは「腕時計業界の穴を埋め、誰もが楽しめるインクルーシブなプロダクトを届けること」。とはいえ単なる「みんなに合う時計」を目指しているのではなく、「これまで排除されてきた誰かのために作る」ことがAndoAndoAndoの真髄。ジェンダーや年齢、手首のサイズといった既存の分類を超えて、時計の楽しさをもっと自由に、もっと軽やかに。「手を使わなくても楽しめる時計」という表現に象徴されるように、そこには実用性だけでなく、ユーモアと遊び心が宿っています。

少量生産で勝負する「マイクロブランド」という新しいカテゴリ
安藤さんが自分のブランドを紹介する際に使っていた「マイクロブランド」という言葉。私にはあまり馴染みがありませんでしたが、小規模な独立系の時計ブランドを指すのだそう。大手ブランドとは異なり、少人数のチームや個人で立ち上げられたブランドが多いのが特徴です。
ロットは1回の生産で数百〜数千本程度で、限定的な数量で製造され、大量生産は行いません。ちなみにAndoAndoAndoでも、一度に数百本のみの生産とのこと。
他にはないユニークなデザインやアイデアを取り入れた時計が多く、宣伝費や中間マージンを抑えることで、高品質ながら比較的リーズナブルな価格で購入できるのも魅力です。
ちょうど私がフィンランドを訪れた5月には、2つの時計フェアが開催されていました。一つはヘルシンキの「The Watch Show Finland」、もう一つはその週末にポーランド・ワルシャワで開催された「Aurochronos時計フェア」。この時期にあわせて、シンガポールのマイクロブランド2社もヘルシンキを訪れていたそうで、タイミングが合えば安藤さんにご紹介いただけるとのことでしたが、残念ながら今回は叶いませんでした。
シンガポールには数多くのマイクロブランドが集まっており、非常に小さな国であるにもかかわらず、そのブランド数は数十社規模にのぼるそう。富裕層が多く、高級時計の所有率が高いことや、公用語が英語で海外向けの発信がスムーズなこともあり、マイクロブランドの集積地としての条件がそろっているようです。
販売は、フェアなどのリアルな場のほか、公式サイトを通じたオンライン直販が中心。安藤さんも、時計フェアに向けて自社製品の魅力を伝えるべく、左右の手首に時計を1本ずつ着けた「二連時計」スタイルで臨んでいたのが印象的でした。


日本にもマイクロブランドはいくつか存在し、たとえば京都発のKuoe(クオ)などが知られています。
クラウドファンディングとマイクロブランドが切り拓く新しいものづくり
マイクロブランドというカテゴリは、まだ知名度が十分とは言えない一方で、ユニークなデザイン性や少量生産体制、そして作り手の思いを伝えるには、クラウドファンディングとの相性が非常に良いのではないかと感じました。
フィンランドもまた、時計業界では「小さな巨人」とも言える存在。人口わずか550万人の国でありながら、世界トップクラスのマスターホロロジャー(時計技巧師)を多数輩出しているのです。その背景には、Kelloseppäkoulu(フィンランド時計学校)という世界的に有名な専門学校の存在があり、毎年少数の卒業生が世界の高級ブランドや独立時計師のアトリエ、あるいは精密機械メーカーなどに進んでいます。手作業による緻密な調整力や高い集中力は、時計製造だけでなく、量子コンピュータの分野にも応用されているとか。
Kickstarterでデビューし、Kibidangoでもプロジェクトを開催したHumismをはじめ、OVDやElectricianzなど、魅力的なマイクロブランドは世界中に広がっていて、調べれば調べるほど奥が深い。そして何より、クラウドファンディングとの親和性の高さをあらためて実感しました。

一方で、こうしたマイクロブランドはまだ広く知られているとは言えず、単に「商品」として紹介してしまうと、本当にそれを求めている人に届かないまま埋もれてしまう可能性もある——そんなことも安藤さんとの会話を通じて感じました。
だからこそ、どうすればマイクロブランドの魅力を「仕組み」として支えられるかを考えたくなったのです。

もう一つ、印象深かったのがフィンランドとロシアの関係についての話題です。
国境を1300kmにわたって接するフィンランドでは、かつてKGBの盗聴器がホテルに仕掛けられていたり、ヘルシンキ大学の一室が冷戦期にはKGBの拠点だったと判明したりと、驚くようなエピソードがいくつもあるそう。
現在もロシアとの緊張は続いており、兵役を終えた人が再び呼び戻されるケースもあるといいます。兵役は拒否も可能ですが、その場合は代替の公共奉仕、さらに拒否すれば刑務所という選択肢まであるというのも印象的でした。
また、対ロシア防衛の文脈では、フィンランドは「15分で対戦車地雷を敷ける」体制を整えているという話や、近年では対人地雷禁止条約からの離脱を決定したというニュースにも触れました。この国にとって「平時」とは、常に一定の緊張感の上に成り立っているのだと実感させられます。
今回のフィンランド出張では、直接安藤さんとお話できたことで、マイクロブランドという世界への理解を深められました。それと同時に、安藤さんの商品づくりにかける思いや、その飾らない人柄に触れられたことが、何よりの出会いだったと感じています。