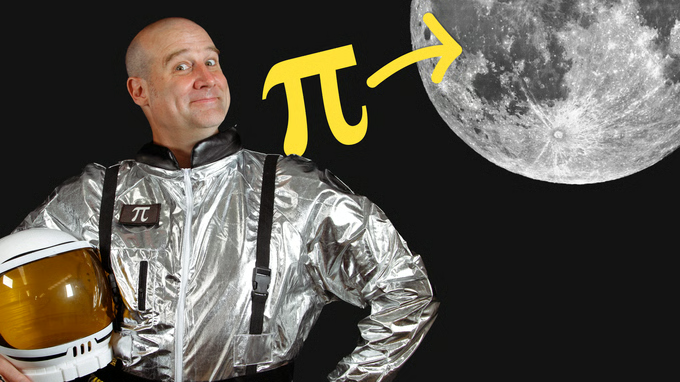宇宙の遥か彼方からやってきた彗星が、私たちの太陽系の彗星とは全く違う「材料」でできていることが分かった。NASAとヨーロッパ宇宙機関が持つ4台の宇宙望遠鏡(超高性能なカメラのようなもの)で同じ彗星を観察したところ、通常の彗星の8倍もの二酸化炭素が含まれていることが判明した。
この彗星は「3I/ATLAS」と名付けられ、2025年7月1日に発見された。太陽系の外から来た彗星としては3番目の発見となる。10月29日に太陽に最も近づく予定だが、太陽の向こう側を通るため地球からは見えなくなってしまう。そのため科学者たちは今のうちに集中的に観察を続けている。
面白いことに、この彗星は予想より早く活動を始めていた。通常の彗星なら太陽にもっと近づいてから氷が溶け始めるのに、3I/ATLASは木星の軌道より外側の、まだ太陽から遠い場所で既に氷が溶け出していたのだ。
4台のカメラで同時に「健康診断」

まるで病院で4人の医師が同じ患者を診察するように、4台の宇宙望遠鏡が同じ彗星を調べた。それぞれ異なる「見方」で観察することで、彗星の正確な成分が分かる仕組みだ。
「ハッブル宇宙望遠鏡」は彗星本体の大きさを測定。直径は約5.6kmで、東京の山手線内側くらいの大きさだった。「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」は彗星から出ているガスの成分を詳しく分析。「TESS」という惑星探査用の望遠鏡は過去の記録を調べ直し、発見前の彗星の動きを追跡した。
最新型の望遠鏡「SPHEREx」は、彗星の周りにできた雲のような大気を観察。この雲は半径23kmまで広がっており、東京から横浜までの距離に匹敵する。
その結果、普通の彗星なら水が多いはずなのに、この彗星は二酸化炭素が水の8倍も含まれていることが判明した。これは今まで見つかった彗星の中で最も高い二酸化炭素濃度だ。
太陽系の彗星とは全く違う「材料」である原因
科学者たちは、この彗星が私たちの太陽系とは全く違う環境で生まれたからだと考えている。遥か昔、別の星の周りで惑星ができるときに、たまたま二酸化炭素の多い場所で形成されたか、長い宇宙旅行の間に宇宙線という放射線を浴び続けて成分が変化した可能性がある。
また、彗星の内部に熱が伝わりにくい構造になっているため、水より二酸化炭素の方が先に溶け出しているという説もある。
観察データは全て研究者向けのウェブサイトで公開されており、世界中の科学者が検証できるようになっている。これにより発見の正確性が高まり、新たな発見につながる可能性もある。
10月に太陽最接近した後は、この彗星は地球に近づいてくる。2026年3月には木星の近くを通るため、木星探査機「Juno」による接近観察も検討されている。火星の周りを回っている探査機からの観察も期待されている。
太陽系の外からやってくる天体の観察は非常に珍しく、私たちの太陽系がどのように形成されたか、宇宙にはどんな環境があるのかを知る貴重な機会となっている。今回の4つの宇宙望遠鏡による連携観察は、限られた時間内で最大限の成果を上げる成功例として、今後の宇宙観測の手本となりそうだ。