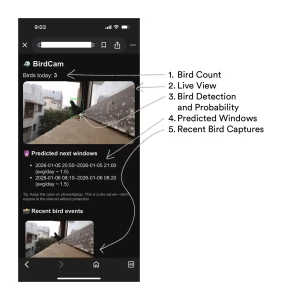先月公開したUSBケーブルチェッカー開発者あろえ氏のインタビュー記事は、SNSを中心に大きな反響を呼んだ。個人開発者が自ら考案したハードウェア製品で成功を収める事例として多くの関心を集めたが、今回もビット・トレード・ワンの協力のもと、また別のケースを取材することができた。
大手電機メーカーで新商品開発に携わる「そーたメイ」氏は、2005年頃から約10年間、社内技術コンペに挑戦。しかし、提案はことごとく採用されず、挫折の連続だった。
転機が訪れたのは2014年。自宅のダイニングテーブルで開発したUSB→Bluetooth変換器「USB2BT」を考案、ビット・トレード・ワンとの協業により10年以上続くロングセラー商品となった。
技術研鑽を最も重視し、個人活動を通じてエンジニアとしての自信を獲得した同氏に、家族の支えを受けながら成功を掴むまでの道のりを聞いた。
USB2BTとは

USB2BT は、USBキーボードやマウスなどの機器をBluetooth対応にする変換アダプターだ。個人だけでなく企業での業務用途に至るまで、安定性の高さが評価されて継続的に売れ続けているロングセラー商品。現在は2代目のUSB2BT PLUSが販売中。
10年間の挫折、あまりにストイック過ぎる技術への思い
――まず、そーたメイさんのお仕事について教えてください。
そーたメイ氏:新卒で国内の大手電機メーカーに入社し、主に新規商品のソフトウェア開発設計を担当しています。過去に電気系、デジタル・アナログIC設計を担当したこともあり、そうした知見を活かしたアーキテクト的な立場になります。元々は機械工学を学びメカ設計専攻として入社したのですが、ソフト部門の配属になり、それ以来20年以上に渡ってソフトウェア開発が仕事のメインです。
――社内の技術コンペへの参加は、いつ頃から始められたのでしょうか。
そーたメイ氏:2005年頃からですね。毎年のように出していたのですが、ずっと落ちまくっていました。なかなかうまくいきませんでしたね。
2014年1月には、50インチモニターを使った技術提案をしました。当時、スマートフォンのアプリをテレビで動かすというコンセプトで、タブレットでタッチ操作できるような仕組みを考えていました。自分としては大きな可能性を感じる企画だったのですが、これも採用されませんでした。
――10年間も提案し続けるモチベーションは、どこから来ていたのでしょうか。
そーたメイ氏:技術研鑽ですね。我々のようなJTC(日系大手企業)の社員だと、エンジニア職であっても自ら設計したり、ソースコードを書いたりする機会が非常に少ない場合があります。
そういうときに、自分の技術の研鑽として個人での活動が一つの選択肢になると考えていました。それに自分のキャリアプラン、40代、50代、60代、定年後に対しても、エンジニアの現場で活躍していくためには、目の前の業務だけじゃなく、長いスパンで見た技術研鑽も大事なんじゃないかという思いもありました。
――当時の市況も厳しかったと思います。
そーたメイ氏:そうですね。入社した1996年あたりは円高の時代※で、倒産する企業も多かった時代です。先が見えない環境下で前に進むためには、立ち止まっていられないというモチベーションがありました。それは私だけでなく、周囲の同僚にもありました。
会社でのミッションをこなしているだけでは生き残れないから、個人としても技術を磨かねばならないーーそういう危機感もありました。
※前年の1995年には1ドル79円を記録。1996年には第二次世界大戦以降、初めて銀行が破綻。製造業や建設業を中心に中小企業の葉酸件数も急増した。
社外への第一歩、秋葉原で見つけた活路
――2014年に転機が訪れたとお聞きしています。
そーたメイ氏:はい。その年の1月の技術コンペも通らず、何かを変えなくてはいけないと思いました。そこで、同年6月の技術コンペでは「そーたメイ」という名義で同人ハードウェア※としての提案をしました。これは技術コンペに対する提案としてはイレギュラーな内容でした。
※同人ハードウェア・・・個人や小規模なサークルが設計・製造・販売するハードウェア製品
具体的に言うと、会社のリソースを一切使わず個人で開発し、身分を明かさずにネット上で作品を公開して、反響を見ながらプロダクト開発を進めるという開発プロセスを提案に盛り込んだんです。
社内の技術コンペ形式では成功するのが難しいから、「会社の枠組みを超えて、同人ハードウェアとして活動する方法もあります」と言いたかったのです。そこにはエンジニアとしてのライフスタイル提案という側面もありました。
――その提案のアウトプットの中に、USB2BTが含まれていたのですね。
そーたメイ氏:元々は2014年の社内コンペで提案したアイデアがベースになっています。USBで接続できる大型のタッチスクリーンモニターとタブレット端末をつなぐさいに、USB経由で取得した情報をBluetoothでタブレットに飛ばすというアイデアでした。しかし、Androidの対応機種が非常に限られていたことや、個人で手掛けるには製品の規模が大きすぎるという課題がありました。
そこで、その企画の一部であるUSB→Bluetooth変換機能だけを切り出して、まずは組立キットとして商品化しようと考えました。2014年5月に、秋葉原の三月兎(当時存在した同人ハードウェアを扱う雑貨店)に持ち込んだのを覚えています。

――そこでビット・トレード・ワン代表の阿部さんとの出会いがあったのですね。
阿部氏(ビット・トレード・ワン):三月兎の方からご紹介いただきました。そーたメイ氏がタッチパネルをBluetoothで飛ばせるというプロトタイプを持ってこられて、それ自体もすごく面白いなと思ったのですが、話していく中で、キーボードやマウスも飛ばせるということが分かりました。
「これならちゃんと作れば、すぐに売れるものになるだろうな」という感触がありました。というのも、非常に完成度が高かったんです。ブレッドボードの試作品ではありましたが、ソフトの完成度が高かったので、製品として耐久性のあるものにすれば売れるだろうと思いました。
――その場で協業が決まったのでしょうか。
そーたメイ氏:そうですね。ビット・トレード・ワンさんをご紹介いただいて、その日に秋葉原のオフィスにお邪魔しました。実は、ビット・トレード・ワンさんの商品は以前から知っていたのですが、個人のプロダクトを委託製造・販売するサービスがあることは知らなかったんです。
タッチモニターとUSB2BTのプロトタイプをお持ちしたのですが、結局タッチモニターの方は店頭展示のスペースなどの関係で難しくて、USB→Bluetooth変換の部分だけで商品化することになりました。それがUSB2BTにつながっていったわけです。
ロングセラーの秘訣は「継続改善が生んだ安定性」

――USB2BTの初代モデルは、どのような仕様だったのでしょうか。
そーたメイ氏:初代の基板は私が設計しました。手はんだの部品実装で、ケースも裸の状態でした。Bluetoothモジュールも外付けのアダプターを使っていたので、お客様に別途用意していただく必要がありました。
阿部氏:初回は300台製造して三月兎さんに半分ぐらい、残りを当社で販売したと思います。思ったよりもよく売れたなという印象でした。
――2018年にUSB2BT PLUSという改良版をリリースされていますね。
そーたメイ氏:初代が思った以上に売れていたので、もうちょっとちゃんとした形で出したいと思いました。Bluetoothモジュールを内蔵して、アクリルケースに収納し、お客様が買ってすぐに使えるような仕様にしました。
ソフトウェアも全部作り直しています。開発期間は半年強ぐらいかかりましたが、私一人でほぼ全部やりました。本業もありましたし、開発規模もかなり大きかったので、時間はかかりましたね。
――USB2BT PLUSでは外装にアクリルを採用されていますが、これはどのような経緯だったのでしょうか。
そーたメイ氏:お客様から「直接基板に触れたくない」という声がありました。ただ、射出成形のケースはイニシャルコストがかかってしまいます。そこでアクリルをカットして組み合わせることで、コスト的にも機能的にも良いものができると判断しました。
阿部氏:当時は今ほどアクリルの委託製造が一般的ではありませんでした。そーたメイさんの勤務先には社内にメイカースペースがあったので、最初の1年ぐらいはそーたメイさんご自身が製造されていました。
そーたメイ氏:勤務先の有志が使える機材を使って、ひたすら製造していましたね。かなり凝ったもので、量産性を考慮しない無駄に複雑な形状をしています。製品のロゴもレーザーカッターを使って、表面に刻印もしてます。自分で管理していたので、こういったデザインができたんです。
――途中から外部委託に変更されたのはなぜでしょうか。
そーたメイ氏:やはり素人製造なので、どうしても品質のばらつきや納期遅延が発生してしまいました。それと、コロナ禍で会社に入れなくなってしまった時期もあって、外部委託という形に変更しました。
最初は自分でやることで、アクリルでやったときにどういった加工ができるか、どういった刻印ができるかといったノウハウを蓄積できました。それを踏まえて外部委託に移行できたのは良かったと思います。
――売上の推移はいかがでしたか。
阿部氏:コンスタントにずっと売れ続けていますね。時期によっては法人から百台単位の大口注文をいただいたこともありました。
そーたメイ氏:初代の販売時には、掲示板を立ち上げて、ビット・トレード・ワンさんと私の両方でお客様からの問い合わせを受ける体制を取りました。お客様から直接「こういう機能が欲しい」「これが動かない」といったフィードバックを受けて、私が直接修正するというやり取りをしていました。
会社ではなかなかお客様と直接お話しする機会がないので、そういった直接のやり取りは非常に新鮮でした。ただ、負担も大きかったので、途中からはビット・トレード・ワンさんにお任せする形になりました。

(画像提供:そーたメイ氏)
――競合製品と比較して、USB2BT PLUSの優位性はどこにあるとお考えですか。
阿部氏:安定性の高さが一番大きいと思います。他社製品もいくつかあったのですが、そーたメイさんが直接お客さんとやり取りしてフィードバックを反映し、ファームウェアの更新も頻繁にやっていたというところが、現在も効いていると思います。
それと、こういった製品は大手メーカーさんがやるには数量的には小規模なんですよね。うちは小ロット多品種のロングテール戦略でやっていますので、小ロット生産でも継続して対応できるというところで差別化できています。
――長期間売れ続けている理由は、技術面だけではないということですね。
阿部氏:そうですね。製品としての完成度もそうですが、継続的にサポートする体制や小ロットでも諦めずに作り続けるという姿勢が、お客様に評価されているのだと思います。
家族と歩む開発人生、ダイニングテーブルから始まった夢
――「そーたメイ」という名前の由来を教えてください。
そーたメイ氏:娘の名前が「めい」で、息子が「そうた」なんです。二人の名前をくっつけて「そーたメイ」にしました。現在、娘は18歳で大学に入ったところ、息子は高校1年生です。
――ご家族のサポートも、これまでに多々あったと伺いました。
そーたメイ氏:最初の頃は娘と一緒にニコニコ動画に投稿したりもしていました。現在は娘も活動から卒業してしまいましたが、妻と協力してワークショップの出展なども続けています。
ワークショップの写真は全部妻が撮ってくれていて、運営も妻と私で行っています。ワークショップで使うキットの製造も、年に数回程度ですが、妻に手伝ってもらうこともあります。
――開発作業はご自宅で?
そーたメイ氏:はい。ダイニングテーブルでやっています。私の部屋が無いので(笑)。今も家族の協力を得ながら開発しています。

――ワークショップ活動も継続されているのですね。
そーたメイ氏:勤務先の社内イベントや一般の工作イベントなどで、電子工作のワークショップを開催しています。参加費は数百円程度で、利益を目的にはしていません。
お客様と直接やり取りできることや、それぞれの方のこだわりやものづくりを見ることができることに喜びを感じています。こういった活動も今後も続けていきたいと思っています。
70歳まで現役エンジニアでありたい
――USB2BTシリーズの成功で、社内での評価にも変化があったとお聞きしました。
そーたメイ氏:「副業」というと、本業がおろそかになるとか、会社にマイナスイメージを与えるのではないかなど問題になるケースもありますが、私の場合は非常にプラスの評価をいただいています。
こういった同人活動が、社内での私の技術アピールや開発活動のアピールにつながって、新しい社内での仕事に発展するなど、すごく良いフィードバックを得られています。実は、USB2BTからの副業収入以上に、そちらの方が大きなベネフィットになっています。
――技術研鑽が主目的だったということですね。
そーたメイ氏:はい。私の活動の本質は、利益を出すのが目的ではなくて、技術研鑽です。新しい発見ができれば、そちらに注力していくし、新しい発見がなければ、他の方に注力するというスタイルでやっています。
USB2BTの成功は、私自身にとって新しいすごく自信になりましたし、対外的にもこういった同人活動がどういう形でプラスになるかというところが、非常にプラスでアピールしやすくなりました。

――今後の目標について教えてください。
そーたメイ氏:私はあと6年半で定年なのですが、それ以降についても、ここまで培ってきた技術的な実力と、そーたメイとしての活動で積み上げてきた実績を活かして、70歳まで現役のエンジニアとして活動していきたいと考えています。
会社を辞めてしまえば、また本当にそこでリセットになりますが、会社の中でやってきたことと、同人ハードウェア的な活動を組み合わせた新しい形で、エンジニアとして第一線で働いていきたいと思っています。
――技術研鑽への思いは、今も変わらないのですね。
そーたメイ氏:はい。現在も新しい大きな挑戦を勤務先に対して提案しています。詳しくはお話しできないのですが、2014年6月にそーたメイとして同人ハードウェア活動の紹介をしたときに匹敵するような提案をしています。
ワークショップ活動も60歳を過ぎても続けていくつもりです。お客様と直接やり取りしたり、それぞれの方のものづくりへのこだわりを見たりすることは、会社でもビット・トレード・ワンさんとのプロジェクトでもなかなか難しいことなので、そういった活動は今後も続けていければと思っています。
ダイニングテーブルから始まった技術者の挑戦は、家族の応援とビジネスパートナーとの出会いにより、大きな成功を収めた。そーたメイ氏の物語は、年齢を重ねても新しい挑戦を諦めず、自分の身の丈に合った環境で努力を続けることの素晴らしさを教えてくれる。そして、成功の定義は経済的な恩恵だけでは無い。自分が認められることも重要なのだ。
長いエンジニア人生の中で温めたアイデアが長く支持される製品となり、開発者自身の人生にも新たな可能性をもたらす。そんな温かい成功物語があった。
関連情報
関連記事